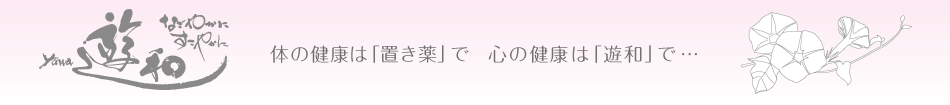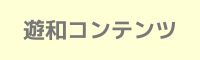「支える力」の要は骨
重力がない宇宙空間では体を動かすための力は必要ありませんが、地球上で自由に体を動かすためには重力に対抗する骨や筋肉、関節などの「支える力」が必要です。中でも骨は支える力の中心的存在だといえます。
骨は70~80%がカルシウムで、残りはコラーゲンやその他ミネラルで構成されています。骨密度の検査では骨内部のカルシウム量を測定しています。
二足歩行の人間は脚に大きな負荷がかかるので、それを支える太ももの骨は体の中で最も太くなっています。また、全身を支える背骨にも大きな負荷がかかるため、S字のカーブを形成することで重力を分散しています。年齢とともに前かがみの姿勢になる人が増えるのは、背骨のカルシウムが減少することで体が重力に負けてS字カーブを維持できなくなっているからかもしれません。
骨の芯部(骨髄)では血液がつくられています。骨の強弱と血液の関係についてはまだ明らかになっていないことも多いですが、骨が弱くなることと動脈硬化の進行度合いは比例しているようです。骨は体を支えるだけでなく、健康の土台であるといえます。

骨は生きている
コンクリートの塊のような印象がある骨も、実は「壊す・つくる」を繰り返している生きた組織です。毎日少しずつ新陳代謝をするので、206個ある全身の骨が入れ替わるには3~5年の期間が必要だとされています。
体内のカルシウムは骨の原料としてだけでなく、神経伝達に欠かせない物質でもあります。そのため、カルシウムが不足すると神経伝達がうまく行われず、血管や筋肉が正常に機能しなくなることが分かっています。
このようにカルシウムは非常に重要なミネラルなので、血液中に必ず一定量存在するよう調整されています。毎日の食事だけで必要な量が補えない場合は、自らの骨を溶かして血液中にカルシウムを補給します。つまり、長期に渡ってカルシウムの摂取量が不足すると、骨はどんどん溶かされて細く弱くなっていくのです。
骨から溶け出たカルシウムは骨づくりには利用されない上に、血管や関節などにくっついてトゲを形成したり血管に沈着して石灰化させたりと、困った特徴があります。