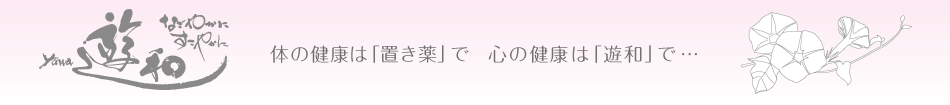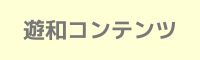自然治癒力の一つ体内の「バランス力」を高めよう
私たちの体にはケガや病気を治して健康を維持する自然治癒力が備わっていて、「支える力」「バランス力」「めぐる力」の3つに分けて考えることができます。今回は体内を適度な状態に保つ「バランス力」について解説します。

バランス力とは
呼吸や血液循環といった生命活動は私たちの意識と関係なく働いていて、環境の変化に合わせて体が適度な状態を保てるよう自動で調節されています。この働きは「恒常性」と呼ばれ、3つの自然治癒力のうち「バランス力」に当てはまります。東洋医学では「バランス力」がきちんと働くことで健康が保たれると考えられています。
「バランス力」は自律神経やホルモン、免疫系などによって調節されるため、これらの働きが乱れるとバランス力は低下して病気の発症リスクが高まったり回復が遅れたりする原因となります。
自律神経によるバランス力
自律神経には、体を活動モードにする交感神経と休息モードにする副交感神経の2つが存在します。これらが均衡を取りながら働くことで、心拍数や呼吸、内臓の働きなど全身の生命活動が調節されています。
生命活動の中でも体温を維持することは生物にとって非常に重要で、マグロや一部のサメなどは常に泳いで運動することで体温をつくり出しています。人間は自律神経の働きで、暑いときは汗や息から熱を発散させて体温を下げ、寒いときは体を震わせて体温を上げています。
しかし、現代社会は空調設備の普及により自律神経が体温を調節する働きは低下しやすくなっています。近年増加している平熱が36度未満の低体温の人や体内に熱がこもって熱中症になってしまう人は、自律神経によるバランス力が低下し体温調節がうまくできていない状態だと考えられます。